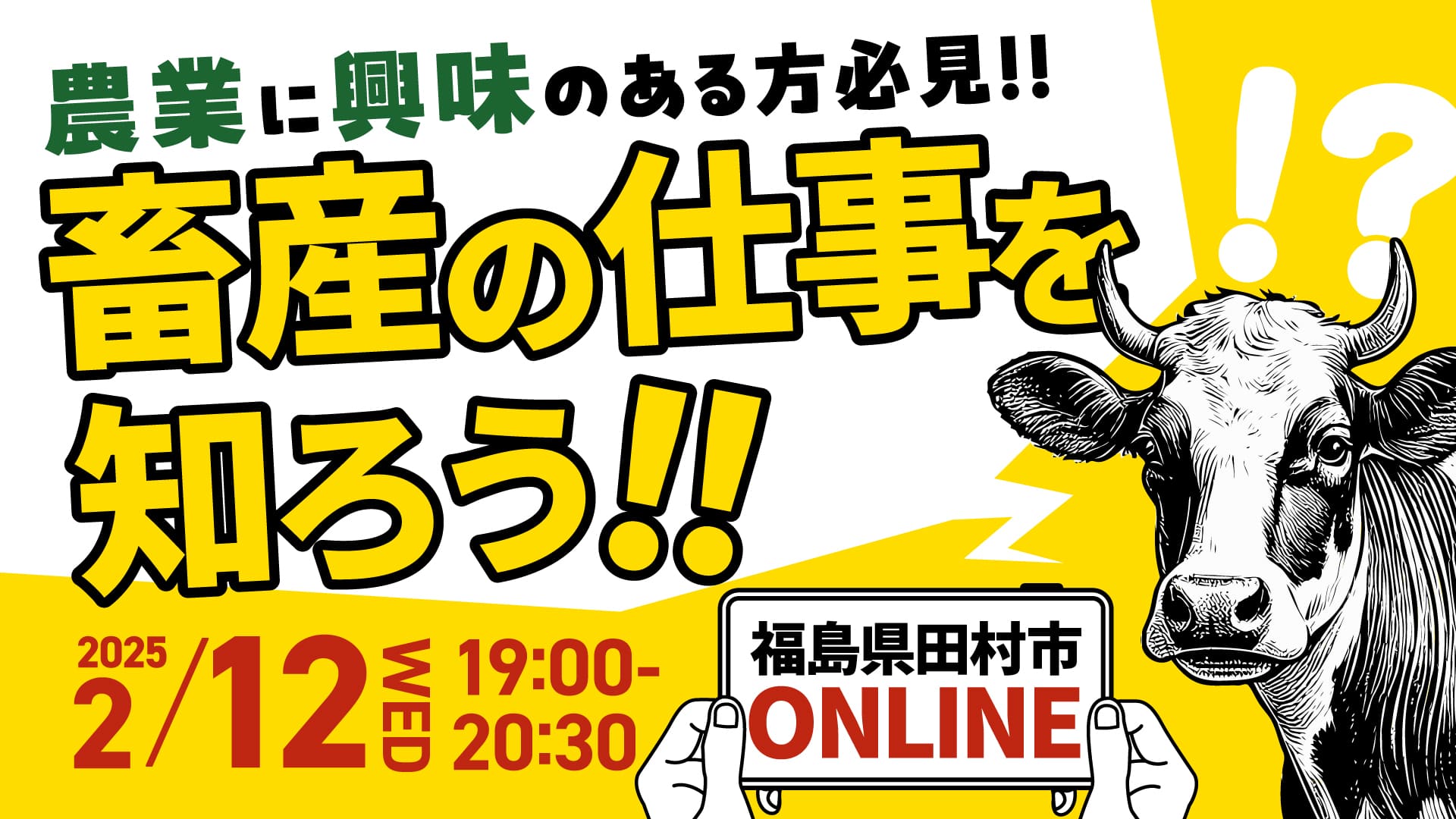2025年2月12日(水) に、私たちの豊かな食生活を支えてくれている「畜産業」にフォーカスを当てたオンラインイベントを開催しました。
今回は、繁殖肉牛経営を行う若手畜産農家の髙橋将志さん(株式会社和農 代表)、田村農業普及所にて窓口を担当している三宅さんと小川さんをゲストにお招きし、畜産業の実情や仕事の魅力についてお話を伺いました。

ゲスト:
・髙橋将志さん(株式会社和農 代表)
福島県田村市都路町で約200頭規模での繁殖肉牛経営を行う若手畜産農家。就農前は、自衛隊に在籍し、退任後は神奈川県でプロのスノーボーダーを目指す傍ら、自動車修理工場で整備士として勤務。震災翌年に帰郷し、長距離トラックの運転手も経験。その後、実家の家業である繁殖農家を継ぎ、2017年に会社を設立した。受精卵移植を活用しながら、自給飼料を基本とした低コスト経営を行い、利幅日本一を目指している。
・三宅巧馬さん(福島県県中農林事務所 田村農業普及所)
「ひとづくり」、「ものづくり」、「地域づくり」の3つの視点から、田村市、三春町、小野町の農業振興に取り組んでおり、畜産の担当として和牛繁殖経営体を中心に畜産農家の皆様の技術的な支援をしている。
・小川佳祐さん(福島県県中農林事務所 田村農業普及所)
「ひとづくり」、「ものづくり」、「地域づくり」の 3 つの視点から、田村市、三春町、小野 町の農業振興に取り組みを行っており、 地域農業推進、経営支援を通して認定農業者や新規就農者の育成など農業の持続 可能な発展に注力している。
いのちを繋いで食の未来を作る『畜産業』
動物を飼い、その動物そのものや生産物を販売する「畜産業」。
主流は牛豚鶏ですが、その他にも羊やヤギ、ミツバチなども畜産に含まれます。
それぞれどのような経営方法があるのかをご説明いただきました。
【令和5年度時点での畜産従事者数の割合】
牛(68.3%):肉牛・乳牛の飼養が中心、和牛ブランドが海外でも人気
豚(11.8%):国産豚肉の生産。養豚場の規模拡大が進んでいる
鶏(5.9%):採卵用と肉用に分かれる。日本の卵消費量は世界トップクラス
その他(14%):馬・ヤギ・羊・ミツバチなどは特定地域で特色ある生産が行われている
■牛について
・繁殖経営
∟繁殖雌牛を飼い、子牛を生産して販売
・肥育経営
∟子牛を購入して肥育し、牛肉を販売すること。
・酪農
∟牛乳やチーズ、バターなどの原料の生乳を生産
■豚について
・種豚経営
∟豚の繁殖・改良などの元となる種豚を生産。企業の研究機関などで行う
・繁殖豚経営
∟繁殖豚の管理と子豚を出荷
・肥育豚経営
∟子豚を肥育し、食用として市場に卸す
※豚に関しては繁殖・肥育を一貫的に行う農家が多い。
■鶏について
・ブロイラー(肉用鶏)経営
∟肉用に鶏を飼育。短期間で効率よく成長し、一般的に約50日(約7週間)で出荷
・レイヤー(採卵鶏)経営
∟養鶏して卵を生産。一般的に生後約5ヶ月から採卵を開始し、約2年で更新。鶏一羽は年間約300個hほど産卵。企業が大規模経営をしている印象
■その他
羊:羊毛やラム肉の生産
ヤギ:ヤギ乳やチーズの生産
ミツバチ:蜂蜜や蜜蝋の採取、ミツバチを使った受粉活動の補助
馬:競走馬・乗馬用馬の育成、馬肉の生産
畜産は未利用資源の活用(牧草や農業副産物などを肉・乳・卵に変換)、資源循環(堆肥化による土壌の肥沃)などの面でも私たちの生活を支えています。また、農業の中でも大きな割合を占めており、畜産業の安定的な発展が求められています。
育てるだけじゃない!畜産家のリアルな一日
──畜産家の一日について教えてください。
髙橋さん:7:00〜17:00が就業時間です。牛を観察してからスタッフ2名で1時間半ほどかけて餌をあげます。その後、牛舎清掃や堆肥出し、消毒、お産補助、餌作り、子牛のミルク作りなどをしますね。そのほか、約100ヘクタール分の水田や畑を借用して自給飼料も生産しています。機械で飼料をあげたりと効率化を進めています。
──お産のタイミングはどのように把握していますか?
髙橋さん:牛の体温を感知してくれるセンサーを使い、体温変化にて把握します。
──畜産の仕事に就くにはどうすればいいですか?
雇用就職:未経験OK。飼育管理や搾乳、出荷作業など。雇用先は畜産農場、酪農組合、大規模牧場、食品会社など。安定した収入が得られる。
独立就農:経験や知識、土地や設備の確保、資金調達、形成計画の策定が必要。経営の自由度が高く、利益を最大化できる可能性あり。
髙橋さん:実家が牛の繁殖農家でしたが継ぐ気がなく、経験も資格もない状態からスタートでした。震災をきっかけに地元に帰ってから家業に興味を持ち、その後、独立して個別に経営を開始。牛舎建設を自分たちで行ったり(通常の1/10ほどに経費削減)、人工授精させた黒毛和牛受精卵を雑種母牛に代理出産させるなどして経費を抑えました。
──畜産で苦労した経験は?
髙橋さん:ゼロからのスタートなので、牛を売るまでの期間(30~40ヶ月)借入をしていた時は不安はありました。それと、牛の分娩が連日夜中に続いたりすると大変です。
──畜産をやっていて一番の喜びは?
髙橋さん:苦労して育てた子牛が売れた時は、喜びもひとしおです。
──どうやって牛の病気を見つけるのですか?
髙橋さん:これは女性の方が得意ですね。鼻水や元気の無さ、熱や便の状態などを確認します。
──人材募集はしてますか?
髙橋さん:随時募集中です。家畜飼料の生産・販売も開始したため、そちらでも募集中です。
【質問】初期費用としてどれくらい借入しましたか?
髙橋さん:5000万円借り、2年間は据え置きで5年で返しました。自分で飼料を作りコストを抑え、高い品質を保って高値で売りながらやってきました。
【質問】何頭からのスタートですか?
髙橋さん:親100頭、子牛100頭。うちでは年間70〜100頭生産しています。
【質問】補助金は使用しましたか?
髙橋さん:牛の餌を作るために水田で使う機械の購入に補助を受けました。
『畜産業』を始める方へのサポート制度も充実

■田村市の就農サポート体制
【全国共通の制度】
・就農準備資金
∟研修期間中の最長2年間、年間最大150万円を交付
・経営開始資金
∟経営開始してから最大3年間、年間150万円を交付
※いずれも対象要件あり
【田村市独自の制度】
・農業者スキルアップ支援事業
∟スキル向上を目的とした視察研修に対して支援(上限5万円)
・新規就農者経営発展支援事業
∟青年等就農計画を達成するために必要な農業用機械・資材の購入などに対して支援(上限50万円)
※いずれも対象要件あり
■農業普及所が行っている普及指導活動
・和牛の生産振興:子育育成管理移動、AI超音波肉質診断
・飼料作物生産拡大支援:飼料作物生産技術指導、組織の運営支援
・その他:飼料の放射線量検査
農業体験で「畜産」の世界に触れてみませんか?

福島県田村市では、オーダーメイド型農業体験in福島県田村市(一泊二日)を開催しております。事前ヒアリングによりご希望や考えをお聞きし、農家さんとマッチングいたします。中長期の体験で就農への不安解消し、就農への第一歩を踏み出してみませんか?
年間を通して受け入れ可能ですので、ご興味を持った方は、ぜひお気軽にたむら移住相談室までご相談ください。
今回もたくさんの方にご参加いただきました。参加者からは、
・畜産業の現状を知れることができてよかったです
・不明点について的確に回答してもらいクリアになりました
・畜産業への就業プロセスが分かりやすかったです
との感想をいただきました。
たむら移住相談室では今後も、田舎での暮らしを満喫されている方や活躍する地域プレーヤーをゲストにお迎えしてオンラインイベントを行います。ぜひ今後の情報もチェックしてみてください。