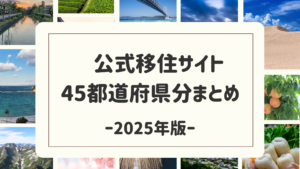「関わりたくなる地域を創る人たち」は、地域の側から様々なテーマや戦略で“関係人口創出に取り組む方たちを、その現場からの想いを交えてインタビュー形式でお届けする新しい連載シリーズです。自治体職員や民間プレイヤーの本音に迫り、その試行錯誤の現場の生の声をお聞きしながら、地域との新しい”関わりシロ”が生まれる現場から、その魅力や可能性を探ります。
初回は北海道・長沼町が2025年9月にスタートした「ながぬま地域起業塾」。そのキーマンであり主担当者である、長沼町 政策推進課 企画政策係 の髙田和孝係長と、その体制を構築し事業の総指揮をとられている 政策推進課 青野直樹課長に、ネイティブ.メディア編集長の倉重がお話を伺いました。
1.地の利を活かした起業をめざす”伴走型起業支援”の新しい形とは
倉重:今回はインタビューに応じていただき、ありがとうございます!きっかけは先日9月1日にEZOHUB東京で行われた、この事業のキックオフイベントでした。会場に60人を超える参加者が集まっていたと聞いて本当に驚きました。あの熱量を実際に拝見して「この事業の狙いや目的をより深く伺いたい」と感じてお声がけしました。
高田さん:ありがとうございます。月曜の夜に天王洲という少し都心から離れた場所で開催したのですが、あれだけ多くの方にご参加いただけて、私たちも本当に驚きました。ありがたいことです。
倉重:では、あらためて「ながぬま地域起業塾」の全体像から教えてください。今回のキーワードは“観光×AI×ローカル”ですね。長沼町の特徴や課題から、どのようにしてこの事業に至ったのでしょうか?
高田さん:はい。長沼町は札幌や千歳などからアクセスが良いことから、年間で約200万人規模の観光客が訪れるポテンシャルがあります。この人流を、如何に地域での滞在や消費につなげられるかが鍵です。そこで、地元の食材を活かした飲食や、道の駅や温泉などの観光資源を生かした新しい事業が生まれやすい環境を、如何に持続的に創っていくかということが、この事業が生まれた最大の狙いですね。
倉重:なるほど。すでに民泊や小売の様々な分野で、移住者の方々が開業されていると伺いましたが、その流れを加速しようというわけですね。
高田さん:そのとおりです。長沼は北海道の中でも移住・定住に関する相談も多い町だと思います。そうした地の利を活かし、起業をきっかけに根づいてもらう。その受け皿としてもこの「ながぬま地域起業塾」を据えています。
倉重:かなり戦略的ですね。今年度からスタートされたばかりだそうですが、その背景はなにかあるんでしょうか?
高田さん:今までは、こうした担い手を、地域おこし協力隊に担ってもらおうと活動してきました。ただやはり起業となると一般的に並大抵のことではありません。長沼でもなかなか任期後に地域に定着しにくいという課題も感じていました。
青野さん:そこは率直に課題だと思っています。だからこそ在任中からトライ&エラーを積み、三年目には町に定着できる事業の形に近づけることが重要です。今回は協力隊だけでなく、町外の起業志望者や副業人材も対象にし、最終的に「長沼を拠点にしたい」と思ってもらえる環境をつくる。そのための“実装の場”として、この起業塾の形を考えてきたんです。
倉重:なるほど、なるほど。起業への伴走の仕組みを整えるのがその目的なんですね。プログラム設計もかなり念入りですよね。オンラインと現地を組み合わせた全13回で、事業計画づくりから資金調達、マーケティング、現地での実証まで相談できる構成になっているようです。
高田さん:実施期間は11月下旬から翌年2月上旬までの約3ヶ月の予定です。オンラインと現地を織り交ぜて進めて、現地回には宿泊費の補助も用意しています。参加者が在職しながらでも通えるよう配慮し、短期集中で手を動かしてやりたい事業のイメージをある程度固めてもらうのが、今回のゴールになっています。
倉重:メンターや協力会社の顔ぶれも幅広いですね。大学、金融、観光・大手企業まで、実務面の相談から資金面までそろっている。協業や投資の機会にもつながる可能性があるそうですね。
高田さん:そうなんです。起業の現場では、最後に“資金”と“実行”の壁が必ず立ちはだかります。そこで地域内外のプレイヤーとつながり、企画から事業化、場合によっては投資・融資までの検討が進められるような機会を提供したいと思っています。地元事業者とのコラボも積極的に後押ししたいですね。
倉重:募集枠を少数精鋭にして、しっかりと伴走しようとされているのがよくわかります。
高田さん:はい。初めてということもあり、今年度はおおよそ8人程度にしぼり、個々の事業プランづくりに深く伴走できればと思っています。すでに現地で活躍している協力隊のメンバーにも運営側でも関わってもらい、参加者をサポートする体制にしています。まずは事業を進めながら、翌年度以降の拡張も見据えてノウハウを蓄積する狙いもあります。
倉重:すでに数多く来訪している観光客をどう町の中心エリアへ引き込むかも課題だと伺いました。やはり街なかでの宿泊や目的をどうつくるかも鍵なんですかね?
青野さん:おっしゃる通りです。だからこそ、観光の直接的なコンテンツづくりだけではなく、町内事業者を支える“地域DX”のような裏方の起業も大歓迎です。事業者の効率化やクリエイティブなどの支援などは、これからAIやテクノロジーの力で大きく変わるはずです。そうした専門家が地域に加わることで、町全体に化学反応が起きるはずです。
倉重:なるほど。“観光×AI×ローカル”は観光事業そのものだけでなく、それを支える仕組みづくりや業務改善も含む広い概念なんですね。結果的に来訪者の滞在時間や消費が町なかに落ち、起業する人の生活圏も町に定着する。
高田さん:そうなんです。観光や宿泊、食、体験づくりに関心がある方はもちろん、バックエンドで支えるエンジニアやマーケターにも来ていただきたいですね。
倉重:これは関心を持たれる人、かなりいそうですね!

(右:高田係長、中:青野課長 左:長沼町PRライターの佐藤さん)
※事業日程・応募方法などの詳細は、こちらの募集記事をご参照ください。
2.“民間で磨いた誘致・育成の勘所”を、行政の現場で活かす
倉重:ここからは、主担当者である高田さんご自身のこれまでの歩みを伺いながら、この事業への思いをお聞きしたいと思います。まず、ご自身キャリアの出発点は民間だったそうですね。
高田さん:はい。最初は札幌の農協でした。札幌は農業者が比較的少ないので、実際の業務は不動産や商業施設の開発が中心でした。地下鉄の駅などの物件を活かした事業や、店舗開発、テナント誘致などを担当していました。
倉重:都市の商業開発の現場で活躍されていたんですね。そこから長沼町役場へ?
高田さん:はい。でも入口は少し変わっていて、最初は教育委員会でした。人材育成の募集に手を挙げて行政に入りました。
倉重:教育分野で組織運営・人材育成を経験し、その後に商工観光の担当部署へ異動されたんですね。ここではやはり民間時代の経験が活かせていますか?
高田さん:そうですね。企業誘致の声かけや関係づくりはわりと得意でしたし、前職時代に築いた人脈やネットワークが今につながっている部分もあります。
倉重:行政の内部で、民間のスピード感とネットワークを持ち込んだわけですね。一方で、役所は“個の色”を出しにくいとも言われますが、そのあたりはいかがですか?
高田さん:はい、やはり役所は一定期間で異動もありますし、“担当者の色”を出しすぎないほうがいいという考えもあるとおもいます。ただ、地域おこし協力隊にしても、今回の起業塾への参加者にしても、やはりある意味自分の人生の貴重な時間をかけて来ていただくわけですし、そこではやはり、”自分自身”としての意気込みや想いも出していかないと、なかなか信じてもらえないなと。とくに今回の起業塾を始めるにあたっては、それを強く意識したところはありますね。
倉重:キックオフイベントも、高田さんの個性が全面に出ていらっしゃいましたね。
高田さん:ありがとうございます。そうですね、やはり自分にしかできない役割を意識し、担当者の顔を積極的に出す発信を意識しています。募集ページやチラシにも課長や担当者の顔をしっかり出して、誰が旗を振っているかを見せるようにしていますね。
倉重:すばらしいですね!やはり、そうあるべきだと思います。
高田さん:“役所”ではなく“人”として向き合うことで、相談の質も具体度も上がります。応募動線づくりでも、誰が伴走するのかが見えると挑戦側も腹が決まる。実際、募集初期から反応があり、既に応募が届き、連絡も来ています。今までご縁のなかった方々からの反応が見えてきたのは大きいです。
倉重:それでも、起業を直接的に支援したり伴走したりするという事業を立ち上げるのは、やはり思い切ったことだなと思うのですが…。よくここまでご決断されましたね。
高田さん:そうですね。確かに簡単ではないですが、前にお話したように、空港や札幌に近いという地の利を活かして、「移住を機に起業したい」という層に具体的な導線を用意できれば、長沼の強みを差別化ポイントに変えられる―そう確信しています。また今すでに素敵な事業を立ち上げている方が数多くいるというのも、自信になったというか、背中をおしてもらっているような気もします。
倉重:たしかに。美味しいだけでなくてオシャレで個性的なカフェや、様々なお店も多いのが本当に印象的でした。これから来られる方にも、その点は本当に勇気や刺激になりそうですね!
高田さん:ええ。ありがたいですね。
倉重:チャレンジしやすいというか、くじけず継続しやすそうな…。
高田さん:はい、そうであればいいなと。例えば地域おこし協力隊の制度もそのあたり工夫していまして、“在任中から”起業準備がしやすいような仕組みも採用しています。与えられたミッションや役割だけに縛られす、早い段階からトライ&エラーを積み、三年目には起業の道筋が見えてくるような制度づくりも試行錯誤してきました。今回の起業塾もそうした発想を起点にしています。より起業しやすい制度やサポート体制が必要だと考えました。
倉重:今回は必ずしも”協力隊にならなければ“というわけでないんですよね。むしろ外部の副業人材や移住検討者にも門戸を開いているという…ここがユニークですね。
高田さん:はい。協力隊をしながらという方も出てくるかもしれませんが、それを前提とはしていません。なので必ずしも移住が必須でもなく、ある意味”関係人口”として長沼町に事業を立ち上げて関わり続けてくれる、強いつながりを生み出す狙いもあるんです。
倉重:環境づくりも本当にすばらしいですね。インタビューさせていただいているここ「ながぬまホワイトベース」は協力隊の拠点施設となるコワーキング施設ですよね。今後は起業塾の参加者もここを拠点に活動できるということですよね。
高田さん:はい、そのとおりです。ここには協力隊だけでなく、協力隊OBでその支援をしているスタッフや、起業の際に相談できる行政書士などの専門家も常駐しています。
倉重:そうなんですね!まさに至れり尽くせりですね!

(ながぬまホワイトベース/左:運営する合同会社マスケン代表の増田さん,右:協力隊支援をする一般社団法人まおいのはこ代表,坂本さん)
高田さん:挑戦しやすい環境づくりを、これからも更に進めて行きたいと思いますし、こうした起業家を生み出すエコシステムのようなものを、この街に根付かせていきたいというのが自分の希望で、最大のチャレンジです。
倉重:個人としての想いも強いですね!
高田さん:行政の立場でも、私はやはり個人としても当事者でいたいです。自分にしかできない役割を引き受け、顔を出して旗を振る。起業をきっかけに長沼を拠点にする人を、一人でも多く増やす。そのために、今までの経験が役に立ったら本当にいいなと思っています。
3.「顔の見える行政」でチャレンジとスピードを生み出す体制づくり
倉重:ここまで伺って感じるのは、行政側の“覚悟”といいますか、それが非常に強く感じられるのはもちろんなんですが、それを実現するための”環境と体制”づくりが非常に緻密でしっかりとされているなということです。
青野さん:高田からもありましたが、協力隊の三年目に「さあ起業を」と言ってもうまくいかないのは不思議ではないですよね。だから在任中にトライアンドエラーができる仕組みを入れたり、協力隊に限らず広く間口を開き、起業の志がある人に注目してもらえる環境をつくろうと考えたんです。
倉重:その「環境づくり」の中核が、高田さんもおっしゃっていた職員が“顔を出す”姿勢だと感じました。やる気と考え方しだいで変えられる…まさにその実践ですね。そうした機運や環境を整えられるのには、ご苦労もあったのではと思いますが…。
青野さん:コロナ後のリセット期に「やってみる」スイッチを入れ直しましたね。予算も、エビデンス一辺倒ではなく、やる気と気合いで取りにいった側面もあるかもしれません(笑)それに応えていただいた町長や議会の皆さんにも感謝ですが…。その期待に応えて本気でやる以上、スピードも熱量も民間並みにできたらと思っていました。
倉重:その実現のために、高田さんをまずはキーマンとして体制に招聘されたわけですね?
青野さん:そうなんです。以前から一緒に仕事したこともあり性格も気心もしれていますし、行政にはなかなかない「民間力」をもっているというか…。この事業はソフト事業ですから、やはり一定の個性と経験をもつメンバーが中心にいる体制づくりが必要だと思っていました。彼ならそれをやってくれるだろうという期待を込めて入ってもらいました。
倉重:人を呼ぶのは、やはり人ですしね。
青野さん:そのとおりです。その他のスタッフももちろん頑張ってくれていますし、いいチーム作りができたんではと思っています。
倉重:その結果、あの熱気あるキックオフイベントになったわけですよね。あのイベントでは「AI」もキーワードとしてかなり目立っていました。この「AI」については、青野さんは具体的にどんな期待をされていますか?
青野さん:先ほど環境づくりについて褒めていただいたんですが、実は長沼町は随分まえからITにも注力していて、例えば今、街のどこでも光ファイバー回線が引ける環境を整えているんです。そういうこともPR不足かもしれませんが、うちの特徴だと思っています。なのでワーケーションなどの環境もかなり整っていると思っています。
倉重:なるほど。その上でのAIなんですね。
青野さん:はい、そうなんです。ただ今回は、必ずしもAIの専門家や、AIを直接使ったサービスを立ち上げてほしいとまでは思っていなくて…。もちろんそういう方がいらっしゃればそれはそれで嬉しいんですが。
倉重:どちらかといえば、高田さんもおっしゃっていたように、観光や飲食・宿泊などの事業にどうAIを活用していくべきかという着眼点ですかね。
高田さん:そうです。AIは、今回の参加者が“やりたい事業”の中で、どこに効くか”を一緒に考えていこうというスタンスですね。その目的で講座の中でもAIの専門家や、既に活用している人の話が聞ける回を用意し、現場で使えるリアリティを感じられるような機会がつくれたらと思っています。
倉重:それも参加者にとっては心強いですね。観光×AIの実装に長けた事業者から話が聞けるのもいいですし、そういうサービスを考えている参加者も来るかもしれませんしね。
青野さん:起業やマーケティングなどをサポートできる外部のプロも巻き込むことも大事かなと思っています。
倉重:そうした面を含めて、自治体の中と外をうまくつなげた体制づくりをされていることに、本当に深く感銘をうけました。
高田さん:ありがとうございます。最終的には「ここで暮らし、ここで事業を続けたい」と思ってもらえるかどうかですね。観光のマーケットにAIで関わる人、起業家を下支えする人、行政で顔を出して走る人――そうした様々な人をつなげてサポートする環境をつくっていけば、自ずとそれを魅力に思ってくれる起業家や、将来それを目指す人たちが集まってくれると信じています。協力隊も起業塾も、そういう人たちが交差して“次の一歩”を踏み出すための、確かな場にしていきたいと思います。

(左:高田係長、右:青野課長 )
編集後記 / 注目される“観光×AI×ローカル”起業支援の本質的なチャレンジ
スタートしたばかりの「ながぬま地域起業塾」。この形に至るまでの試行錯誤には、様々な課題意識や調整、挑戦があったことがわかりました。その結果、思いつきの薄っぺらい企画とは大きく異なる、地の利を活かした事業を地域に根ざすための念入りな戦略と、制度設計、また自治体内外の人を最大限活用した体制づくりや、ハードの整備など、長年にわたる準備の上に始まったものだと確信しました。
今後ますます”関係人口”を増やそうという動きが各地で加速するでしょう。当たり前ですが、それは一朝一夕ではなし得ません。どういう人に対して、どんな環境を提供し、何をしてもらってどんな関係を構築するのか。その設計が緻密でかつ地域性が明確なほど、人は惹きつけられます。長沼町のこの取り組みを拝見すると、地域が本当に何を求めているのかを考え、そのためにできることを一歩一歩積み上げていくことこそ、本質的な取り組みができるんだと改めて痛感します。
その試行錯誤はこれからも続くでしょう。しかしそれに携わっている皆さんの気持ちの強さや、自治体の既成概念を覆すくらいのパワフルさからは、近い将来大きな実効性を生み出す可能性を強く感じました。これからもこの事業にはぜひ注目させていただきたいと思います。
この魅力あふれる長沼町での起業に少しでもご興味のある皆さんは、こちらを参考の上、ぜひお問い合わせ下さい。
また最新情報は、こちらの「ながぬま地域起業塾 公式インスタグラム」をご参照下さい。