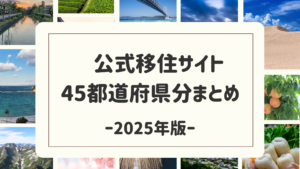東京生まれ東京育ちの大嶋憲人さんは、今、広島県東広島市を拠点にレモンをはじめとした一次産品の販路づくりを担う「産地コーディネーター」として活動しています。全身黄色の服に、黄色い軽バン。まちを走るだけで目を引くその姿から、地元では「レモ兄(れもにい)」の愛称で親しまれています。高齢化や担い手不足が進む中山間地。6次産業化という言葉が広がり、「作る・伝える・売る」を農家自身が一手に担うことが理想とされてきましたが、現実には「生産だけでも手一杯」という声も少なくありません。そこで大嶋さんは、生産者と消費者の「あいだ」に入り込む“専属エージェント”のような「産地コーディネーター」という役割を自らつくり出し、日々走り回っています。
一方で、世の中ではAIをはじめとするデジタル技術が急速に進化し、「人とAIの役割の違い」や「人がやることで価値のある仕事とは何か?」など議論されています。本記事では、Nativ.media編集長の倉重が、大嶋さんのこれまでのストーリーと、AI時代にあえて“人の手触り”にこだわる仕事観をたどりながら、「地方と関わりたい」「一次産業を応援したい」と考える読者が、一歩を踏み出すヒントを探っていきます。
東京育ちの“レモ兄”が、広島・東広島に飛び込むまで
倉重: 今日はお時間をいただき、ありがとうございます。まずは、今どこでどんな暮らしと仕事をしているのかから伺ってもいいですか?
大嶋: はい、もちろん。今は広島県の東広島市を拠点に、一次産業の支援をする仕事をしています。農家さんだけじゃなく、漁師さんや畜産農家さんも含めて、「オールジャンル」で関わっています。
倉重: 一次産業といっても幅広いですよね。具体的には、どういう支援をしているんでしょう。
大嶋: なかなか自分たちだけでは販路をつくれない生産者さんの代わりに、新しい売り先を探してきて、つないでいく役割です。自分が卸業者のような立場で仕入れて、飲食店さんに卸したり、オンラインショップで販売したりと、販売代行に近いことをしています。
倉重: いわゆる「作る人」が、自分で販路まで全部やるのは相当な負担ですよね。6次産業という言葉もありますが、むしろ二次・三次の部分を引き受けているイメージでしょうか。
大嶋: そうですね。生産のプロである農家さんや漁師さんに、全部を背負わせるのはやっぱり難しい。「いいものを作る人」と「それを届ける人」を分けて、それぞれの得意な部分に集中できるようにしたい、というのが出発点でした。
広島県東広島市のまちでは、全身黄色の服に黄色い車で走り回る彼の姿が、少しずつおなじみになりつつあります。産地コーディネーターの大嶋憲人さん。地元では「レモ兄」の愛称で呼ばれています。インスタグラムのフォロワーは約3,000人。市役所の職員や飲食店の人から「いつもSNS見てます」「レモ兄ですよね?」と声をかけられることも増えてきました。初対面なのに、すでに名前と顔が一致している。そんな“顔の見える関係”が、少しずつ広がっています。

[レモ兄こと大嶋さんが支援する農家さんと]
倉重: もともとは、ずっと東京で暮らしていたと伺いました。そこからどうして東広島にたどり着いたんですか。
大嶋: 生まれも育ちも東京なんです。大学は農学部で、野菜の研究をしていました。新卒で入ったのは食品メーカーの法人営業で、その次の会社では、スーパーマーケット向けの農産物ブランドをつくる仕事をしていました。
そこでプロモーション担当として、全国の提携農家さんや漁師さんのところへ行って、インタビュー動画をつくる仕事なんかをしていたんです。
倉重: 大学のころからずっと、「食」と「一次産業」に関わってきたわけですね。実際に現場に足を運ぶ機会も多かったんでしょうか。
大嶋: はい。産地に行って畑や漁場を見せてもらいながら、採れたてのものをその場で食べていました。現場で味わうと、同じ野菜でも本当においしさが違っていて。その魅力をどう伝えるかを考えるのが、すごく好きだなと感じたんです。「これは自分に合っているな」と思いました。
倉重: 畑や海のそばで食べると、まったく別物ですよね。その延長線上に、今の「産地コーディネーター」としての活動がある、という感覚でしょうか。
大嶋: そうですね。畑で採れたてを食べたときの感動が、自分の中ですごく大きかったんです。その体験を自分だけのものにしておくのは、もったいないなと感じました。自分の手で届けられたら、食べる人にとってもうれしいし、農家さんにもちゃんと還元できる。そのイメージが今の仕事の原点ですね。
大嶋さんには、「毎年みかんや梨が箱で届く地方の親戚」がいるわけではなかったそうです。友人から「実家のみかんが段ボールで送られてきた」「今年も梨が届いた」と聞くたびに、「いいなあ」とどこか羨ましく思っていました。もし日本中に、「季節の果物や野菜を送ってくれる親友」がいたらどうだろう。そんな妄想をしながら、いつか自分も誰かにとってそういう存在になれたらいい──。いまのレモ兄のスタイルには、その感覚が色濃く反映されています。

[サラリーマン時代の大嶋さん]
倉重: 広島とは、どんなきっかけでつながったんですか。
大嶋: ご縁なんですけど、広島県の大崎上島にいるレモン農家さんとご一緒する機会があって、そこで少しずつ仕事をさせてもらうようになりました。「今度は広島に来て、一緒に一次産業の支援をやろうよ」と声をかけてもらったのが出発点ですね。
倉重: そこから一気に「移住」まで進んだわけですね。最初から住まいを決めて移ったわけではなかったと聞きました。
大嶋: はい。広島に関わり始めたのは去年の4月なんですが、最初の2カ月くらいは、あえて住まいを決めなかったんです。車に寝袋を積んで車中泊で過ごしながら、「どんな産地があって、どんな人たちがいるのか」を見る期間にしました。
倉重: 車中泊で産地巡りって、なかなか攻めた入り方ですよね(笑)。そこで見えてきた景色は、どんなものだったんでしょう。
大嶋: 前職で関わっていたのは、長野のレタスや北海道のじゃがいもみたいな「一大産地」が多かったんです。大規模で工業化も進んでいて、太い販路もすでにできている。もちろんそこにはそこなりのやりがいもあるんですが、「自分のキャリアや時間を本当に必要とされているのは、むしろ見えにくい小さな産地なんじゃないか」と思うようになりました。広島の中山間地を回っていると、高齢化や担い手不足、耕作放棄地といった課題が目に見える形で広がっていて、「これは結構やばいな」という危機感がありました。
倉重: 同じ「農業」でも、見えている世界がまったく違ったわけですね。
大嶋: そうですね。2カ月、車であちこち回りながら見ているうちに、「これはもう現場の近くに住んでやらないと難しい」と腹をくくるようになりました。だったら、しっかり腰を据えてやろうと決めて、東広島を拠点に選んだ、という流れです。
倉重: 東京では安定した仕事もあったと思いますが、不安はありませんでしたか。
大嶋: もちろん不安でした。でも今はまだ独身で、身軽なタイミングでもあって。「ここでこういう選択ができるのは、多分人生で最後のチャンスだな」と感じたんです。食や農の業界にはこの先も関わり続けたいと思っていましたし、自分の目でもっとリアルな現場を感じたい気持ちが強かった。だったら一度ちゃんと、「現場のそば」に身を置いてみようと。
倉重: 20代のうちに、思い切って舵を切ったわけですね。
大嶋: そうですね。東京にいたままでも、それなりに安定したキャリアは描けたと思います。でも、「5年後、10年後にこの地方の景色は残っているのか」と考えたときに、自分の人生の時間をここに投じてみたいと本気で思ったんです。
こうして東京から東広島へと拠点を移した大嶋さん。今では黄色い車で山間部から瀬戸内の沿岸部まで走り回りながら、レモ兄として、生産者と街の食卓のあいだを行き来する日々を送っています。

[クラウドファンディングで発送拠点に改修した東広島・豊栄町の古民家]
「産地コーディネーター」という仕事。農家と食卓をつなぐ新しい役割
倉重: さっき「販売代行に近い」とおっしゃっていましたが、もう少し具体的に、どんなものをどこに届けているのか教えてもらえますか。
大嶋: 看板商品はレモンなんですけど、同じ広島県東広島市の産地でいうと、ほかのみかん類の柑橘、じゃがいも、トマト、ピーマン、ナス、玉ねぎなど、地域で育つ野菜をオールジャンルで仕入れています。商店街で露店販売をすることもあれば、飲食店さんに卸したり、ネットで個人のお客様に届けたりもしています。
倉重: 農家さんの開拓はどうしているんですか?
大嶋: 基本的には「足」で稼いでいます。紹介の紹介でつながることもありますが、時には畑で作業しているおじちゃんに飛び込みで「こんにちは!」って声をかけることもありますよ(笑)。「ここでこういう活動をしていて、美味しいものを探しているんです」って。
倉重: 飛び込み営業ですか! それはなかなか勇気がいりますね。でも、そうやって直接顔を合わせるからこそ、ネットには出回らない逸品に出会えるのかもしれません。
大嶋:本当にそうです。やっぱり畑に行って、その場で採れたてのものを食べたときの感動ってすごいんですよ。その感動を自分の中に留めておくのは、もったいないんです。だからこそ、「どうやったらこのおいしさを、そのまま誰かの食卓まで持っていけるか」を、いつも考えています。
倉重: 「安く仕入れて高く売る」という一般的な卸売とは、少し違うスタンスを感じます。レモ兄が間に入ることの付加価値って、何だと考えていますか。
大嶋: 自分の中では、「情報」と「鮮度」、それに「物語」です。市場を通すとどうしても時間がかかりますし、誰が作ったものなのかが見えにくくなってしまう。私が間に入ることで、朝採れのものをその日のうちに飲食店さんに届けたり、「この農家さんはこういう想いで作っているんです」という情報を写真や文章と一緒にセットで提供したりできます。
倉重: なるほど。単に野菜という「モノ」を右から左へ流すのではなく、その背景にある情報という「コンテンツ」も一緒に販売しているわけですね。
大嶋: おっしゃる通りです。自分でSNSの発信や写真撮影ができる農家さんは、ご自身でやればいいと思うんです。でも、作る腕は超一流なのに、情報発信や営業は苦手という方も多い。そういう方の代わりに、商品の魅力を翻訳して届けるのが自分の役割です。
飲食店さんには、食材を届けるだけじゃなくて、メニューに載せるための農家さんの顔写真を提供したり、紹介文を書いたりといったサポートもセットで行っています。「この生産者さんから仕入れた食材です」と説明できることは、お店の信頼やブランドにもつながりますから。
大嶋さんは、活動の拠点づくりにも力を入れています。半年ほど前にはクラウドファンディングを行い、東広島の北部・豊栄町(とよさかちょう)にある築100年ほどの空き家を改修。そこを食材の保管場所兼、発送拠点にしました。山あいの小さな集落に立つ古民家に、レモンや野菜が集まり、そこから全国の食卓へと旅立っていきます。
倉重: 空き家の改修まで! まさに地域に根を張っていますね。そうやって地道に活動を続けてきて、農家さんとの関係性に変化はありましたか?
大嶋: 最近、本当に嬉しいことがあったんです。東広島のとある地域でレモンを作っている農家さんがいらっしゃるんですが、私が毎週のように通って、レモンを仕入れては販売しているうちに、ある日その方が「今後、新規で取引したいという話が来たら、全部レモ兄を通してくれと案内することにしたから」と言ってくださったんです。
倉重: ええっ、それはすごい! つまり、専属エージェントのような立場を任されたということですよね。
大嶋: はい。それを聞いた時は、本当に涙が出るほど嬉しかったですね。「ああ、ここまでやってきてよかったな」と心から思いました。単にたくさん買ってくれるから、という理由だけではなく、私が汗をかいて販路を開拓したり、レモンの魅力を発信したりしている姿を見て、信頼してくださったんだと思います。
倉重: 「卸問屋」としても、生産者からそこまで信頼されるというのは、最高の名誉ですね。大嶋が目指している「産地コーディネーター」という仕事の輪郭が、少しずつ明確になってきた気がします。

[レモ兄の活動の様子]
AI時代にこそ残る“人の仕事”。移住がくれた使命感とこれから
倉重: 大嶋のお話を聞いていると、ビジネスモデル自体はとても現代的なんですが、やっていることはかなりアナログで泥臭い印象もあります。今は世の中的にAIやITで効率化しようという流れが強いですが、そこについてはどう考えていますか。
大嶋: もちろん、SNSでの発信や事務作業などでITツールはフル活用しています。でも、あえて「人が介在すること」にこそ、これからの価値があると思っているんです。
倉重: 人が介在する価値、ですか。
大嶋: ええ。最近はYouTubeなどを見ていても、AIが作った動画なのか人間が作ったものなのか区別がつかないことが増えていますよね。文章も画像も、AIがどんどん上手になっていく。だからこそ、例えば届いた段ボールの中に手書きの手紙が一枚入っているとか、そういう“人の手触り”に価値が戻ってくる時代が来るんじゃないかなと感じています。
倉重: たしかに、AIが当たり前になればなるほど、「誰が」「どんな思いで」届けてくれたのかが、より大事になっていきそうです。
大嶋: そう思います。自分はよく「田舎にいる親友みたいな存在になりたい」と言うんです。昔なら、田舎のおばあちゃんや友達が、季節になるとミカンや野菜を段ボールに詰めて送ってくれたりしましたよね。あの感じを、今の時代にもう一度ちゃんとやりたい。全国各地に、「美味しいものが獲れたから送るよ!」って言ってくれる親友みたいな存在がいたら、人生もっと豊かになると思いませんか? 自分はその一人になりたいし、そんな“親友”の輪を広げていきたいと思っています。
倉重: それは素敵ですね。単なる通販ではなく、「あいつが選んでくれたから美味しいはずだ」という信頼関係で成り立つやりとり。それを仕事として成立させようとしているわけですね。
大嶋: そうです。AI時代には、逆にそういう人間くさいコーディネーター職こそが、代替されない最強の職業になるんじゃないかと思っています。
倉重: 冒頭でも少し話しましたが、この仕事って「AIには代替されない仕事だ」と感じています。人と人の間を行き来して、関係性をつくりながら物を動かしていく。少なくとも50年、もしかしたら100年くらいは、しっかり必要とされる役割なんじゃないかと。
大嶋: そうだといいですね。ビジネスモデル自体はシンプルなんですけど、求められるスキルセットは結構多様だと思っています。交渉力やコミュニケーション力、情報発信の力、それからビジネスとして成り立たせる感覚も必要で。どれか一つが欠けても、うまく回らない仕事だなと感じています。
倉重: さらに言えば、ITにもある程度精通していないとできないですよね。プログラミングをバリバリやるわけではないにせよ、発信やEC、業務効率化のためのITツールは避けて通れない。
大嶋: そうですね。だからこそ、「人の間を行き来する仕事」が最後まで残るのかな、とも思います。テクノロジーを使いこなしつつ、人と人の間にちゃんと入り込める人材が、これからの地方にはもっと必要になる気がします。
倉重: 今後の展望としては、どのような未来を描いているのでしょうか。
大嶋: まずは、ここ東広島のポテンシャルをもっと引き出したいですね。実は東広島ってすごいんですよ。北に行けば雪が降ってリンゴが採れて、南に行けば瀬戸内の温暖な気候でミカンやレモンが採れる。ひとつの市の中でこれだけ気候と作物の幅がある地域は、全国でも珍しいんです。
倉重: へえ、それは知りませんでした! リンゴとレモンが同じ市内で採れるというのは確かに面白いですね。
大嶋: そうなんです。だからこそ、「北のリンゴと南のレモン」をセットにして届けるといった、東広島ならではの企画ができます。こういう組み合わせは、生産者同士がそれぞれの畑にいるだけでは生まれにくくて、コーディネーターが間に入るからこそ生まれる価値です。「東広島ブランド」として、この面白さをもっと外に発信していきたいですね。
倉重: それを大嶋一人で?
大嶋: いえ、一人の限界も感じているので、ゆくゆくはチームを作りたいと思っています。東広島には大学が3つあって、地域活動に興味がある学生さんも多いんです。ただ、どうしても今の農業ボランティアって、体験して終わりになってしまいがちで、仕事になるイメージが持てない。だからこそ、できれば自分がまずビジネスとして成功例を作って、「産地コーディネーターはちゃんと食える仕事なんだ」と証明したいんです。販売が得意な人、写真や動画が得意な人、ITや情報発信が得意な人。それぞれの強みを活かしてチームを組み、地域全体で一次産業を盛り上げていく。そんなエコシステムを作れたら最高ですね。
倉重: 大嶋がファーストペンギンとなって、後に続く道を作っているわけですね。最後に、移住や二拠点生活に興味はあるけれど、一歩を踏み出せていない読者に対して、何か伝えたいことはありますか。
大嶋: 自分も、東京で安定した会社に勤めていた頃は、まさか広島に移住してレモンを売っているとは思っていませんでした。でも、現場を見て「このままだと、本当にこの景色がなくなるかもしれない」と感じたときに、まだ独身で身軽だったこともあって、「この選択ができるのは人生で今が最後かもしれない」と思ったんです。
移住したからといって、毎日がキラキラしているわけではないですし、正直しんどいことも多いです。でも、自分の足で現場を回って、生産者さんと一緒に汗をかきながら、日本の食卓を支える仕事ができている実感はあります。
迷っている人がいたら、「完璧な準備が整うのを待つより、まずは小さく関わってみる」のも一つの方法ですよ、と伝えたいですね。たとえば、どこか一つ「応援したい産地」を決めて、定期的にその地域のものを買ってみるとか。それだけでも、十分立派な一歩だと思います。
倉重: AI時代だからこそ求められる「人の仕事」としての産地コーディネーター。その等身大のリアルを、しっかり伺えたと思います。ありがとうございました!

編集後記
鮮やかな黄色の衣装で東広島の畑を駆け回る「レモ兄」こと大嶋憲人さん。そのユニークな姿とは裏腹に、語る言葉は非常に論理的で、そして地域への深い愛情に満ちていました。
印象的だったのは、そのスタンスがボランティアではなく、あくまで「職業」としての一次産業支援だということです。農家や漁師が生産に集中できるよう、販路開拓や情報発信を丸ごと引き受ける存在として、自らの役割をデザインし直している姿は、地方での新しいキャリアモデルの一つに見えました。
効率化とAI化が加速する現代において、あえて「手間」と「対話」を重視し、生産者と消費者の間に温かい人間関係を再構築しようとする彼の取り組みは、単なる農産物の販売代行ではありません。失われつつある「人と人との繋がり」による、新しい時代の価値創出の試みだとも感じます。
「5年後、この景色はあるのかな」と大嶋は言いました。東広島の山あいに広がる段々畑や、瀬戸内の穏やかな海辺の風景。その背景には、日々畑や海に立つ人たちの暮らしがあります。地域からの豊かな食文化を守り、次世代に繋いでいくためには、レモ兄のような「産地コーディネーター」の存在が、これからますます不可欠になっていくでしょう。
そしてこの物語は、東広島だけの話ではありません。日本各地の中山間地や小さな産地でも、「作る人」と「食べる人」の間をつなぐ役割は、まだまだ足りていません。
読者のみなさんにとっても、「誰かの一次産業を応援してみる」「好きな産地と継続的につながってみる」といった、小さな一歩を考えてみるきっかけになればうれしいです。その先に、新しい仕事や生き方の選択肢が見えてくるかもしれません。
ここまで読んでいただきありがとうございました! では、また次回のNativ.Life Interviewでお会いしましょう。
文責:ネイティブ.メディア編集長 倉重
※Nativ.Life Interviewシリーズ 過去の3本の記事はこちらから。